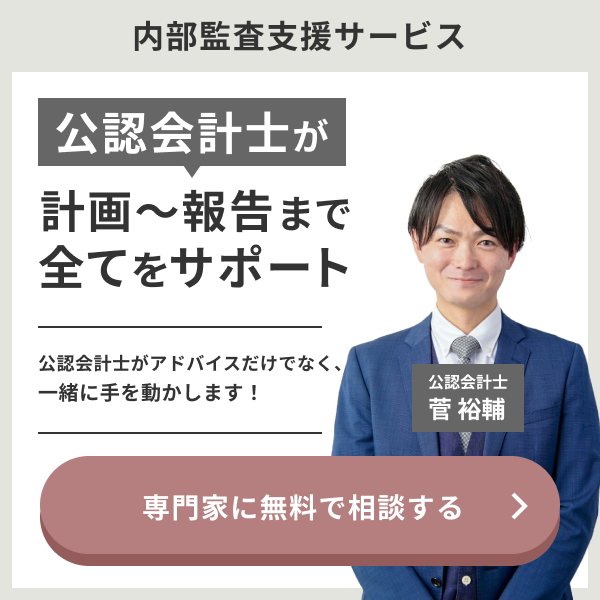内部監査とは?目的から実施手順まで企業の成長を支える仕組みを解説
内部監査とは企業の健全な成長を支える重要な仕組みです。本記事では内部監査の目的や外部監査との違い、具体的な実施手順について詳しく解説します。IPO準備企業から上場企業まで、実効性の高い内部監査体制を構築するためのポイントをご紹介します。
企業の持続的成長において、内部監査は単なる「チェック機能」を超えた戦略的な役割を担っています。特にIPO準備企業や上場企業にとって、内部監査は投資家からの信頼獲得と経営の透明性確保に不可欠な要素です。
しかし現実には、「毎年同じチェックリストの使い回しになっていないだろうか」「指摘はするものの、なかなか本質的な改善に繋がらない」といった悩みを抱える企業が少なくありません。近年、コーポレートガバナンス・コードの改訂やJ-SOX(内部統制報告制度)の改正により、内部監査に求められる役割は大きく変化し、その重要性はますます高まっています。
この記事では、内部監査の基本概念から実践的な実施手順まで、そして多くの企業が直面する形骸化の課題とその解決策を含めて、経営管理に携わる方々が知っておくべき重要なポイントを解説します。
内部監査とは何か
内部監査とは、企業内の独立した組織が自社の業務活動を客観的に評価し、経営目標の達成に向けた改善提案を行う仕組みです。具体的には、社内の監査部門や監査役が中心となって、財務会計や業務プロセスの適正性を検証し、発見された課題について経営陣に報告・提言を行います。
三様監査の観点からの整理
企業の健全な経営と統治(コーポレート・ガバナンス)を支える仕組みとして、「三様監査」という考え方が重要です。これは、以下の3つの監査機能が、それぞれの独立した立場から役割を果たしつつ、相互に連携・協力する体制を指します。
- 監査役(会)監査: 取締役の職務執行が法令や定款に違反していないか(適法性)などを監査する。
- 会計監査人監査: 企業の財務諸表が適正に作成されているかを、独立した第三者の立場から監査する。
- 内部監査: 経営目標の達成に貢献するため、業務プロセスの有効性や効率性、リスク管理体制などを評価・改善する。
この三様監査の枠組みにおいて、内部監査は業務執行の最前線に最も近い立場から、組織内部のリスクや問題点を早期に発見し、改善を促すという重要な役割を担います。
監査役や会計監査人が主に経営層の監督や財務諸表の信頼性確保といった観点から監査を行うのに対し、内部監査はよりミクロな視点で日々の業務活動に踏み込みます。そして、内部監査によって得られた情報は、監査役や会計監査人にとっても重要な判断材料となります。
このように、内部監査部門が監査役や会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査計画や結果を共有することで、監査の重複を避け、指摘事項に対する改善をより確実なものにすることができます。三者が効果的に連携することで、経営に対する多角的で重層的な監視が可能となり、企業統治全体の実効性が高まるのです。
内部監査の役割と重要性
内部監査の本質は「自浄作用」の強化です。 これは、会社自身で不正や誤りといった問題を発見し、適切な改善策を講じて、正常な状態に戻すことができる力を指します。上場審査においても、この自浄作用の有無が最も重要な評価ポイントとなっています。
近年の環境変化により、内部監査に求められる役割は大きく変化しています。責任範囲の拡大として、これまでの社長への報告だけでなく、取締役会や監査役会へ直接報告を行う「デュアルレポーティング」が求められるようになり、経営における監視機能としての役割が強化されています。
また、求められるスキルの高度化も重要な変化です。内部監査人には「熟達した専門的能力」と「専門職としての正当な注意」が明確に求められ、単に決められた項目をチェックするだけでなく、業務の問題点を的確に指摘し、納得感のある説明で改善まで導く「助言・提言能力」が不可欠となっています。
外部監査との違い
内部監査と外部監査は、実施主体や目的において明確な違いがあります。以下の表で両者の特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 内部監査 | 外部監査 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 社内の監査部門など | 公認会計士・監査法人 |
| 主な目的 | 業務改善・リスク管理・自浄作用の強化 | 財務諸表の適正性証明 |
| 法的位置づけ | 法的規定なし(任意) | 金融商品取引法・会社法に規定 |
| 監査対象 | 全業務プロセス | 主に財務会計処理 |
| 報告先 | 経営陣・取締役会 | 株主・投資家等利害関係者 |
| 実施頻度 | 年間を通じて継続的 | 年次(決算期) |
| 評価の視点 | 自律的運営能力・改善提案 | 財務情報の信頼性 |
外部監査が株主や投資家に対する財務情報の信頼性を保証する役割を担うのに対し、内部監査は経営陣が自社の状況を正確に把握し、継続的な改善を図るための内部管理ツールとして機能します。
監査役監査との違い
監査役監査と内部監査も、監査対象と実施範囲において重要な違いがあります。監査役監査は会社法に基づく法定監査であり、主に取締役の職務執行の適法性を監視することが目的です。一方、内部監査は全従業員の業務活動を対象とし、適法性だけでなく効率性や有効性も評価します。
監査役監査では、取締役会での意思決定プロセスや重要な契約の締結手続きなど、経営レベルの行為が主な対象となります。これに対して内部監査は、現場レベルの日常業務から経営戦略の実行状況まで、より幅広い領域をカバーします。
両者は相互に補完し合う関係にあり、監査役は内部監査の結果を活用して効率的な監査を実施し、内部監査部門は監査役からの指摘事項を監査計画に反映させることで、企業全体のガバナンス強化を実現しています。
内部監査の目的と効果
内部監査の目的は、企業の持続的成長と価値創造を支援することです。具体的には、リスクの早期発見と対応、業務プロセスの最適化、そして経営戦略の効果的な実行を通じて、企業の競争力強化に貢献します。
現代の企業経営においては、事業環境の変化スピードが加速し、新たなリスクが次々と出現しています。生成AIやサイバーセキュリティなど、従来の監査項目では対応できない新しいリスクも生まれており、内部監査は企業の「免疫システム」として、これらの変化に適応し続ける必要があります。
不正防止とリスク管理における自浄作用の強化
内部監査の最も重要な機能は、企業の自浄作用を育成することです。自浄作用とは、会社自身で不正や誤りといった問題を発見し、適切な改善策を講じて、正常な状態に戻すことができる力を指します。
しかし、多くの企業では内部監査が形骸化し、過去のチェックリストを毎年使い回している状況があります。これでは、リスク評価が更新されず、現状に即した監査ができません。また、生成AIやサイバーセキュリティなど新たなリスクに対応できていないケースも頻繁に見受けられます。
効果的な不正防止を実現するためには、単に規程違反を指摘するだけでなく、不正が発生しやすい環境や要因を分析し、根本的な改善策を提案することが重要です。そのためには、被監査部門の業務理解を深く行い、踏み込んだ指摘ができる専門性と、本質的な問題解決に繋がる助言能力が求められます。
IPO審査では特に自浄作用の存在が厳格に評価されます。審査機関は、上場後に主幹事証券のサポートがない状況でも、企業が自律的に課題を発見し、改善できるかどうかを重視しています。この能力こそが、長期的な企業価値向上の基盤となるからです。
業務効率化の促進
内部監査は業務プロセスの客観的な評価を通じて、効率化の機会を発見し、生産性向上に貢献します。しかし、多くの企業では指摘が形式的で、本質的な問題解決に繋がっていないという課題があります。
これは、監査人の知見不足により根本原因にアプローチできていないことが原因です。効果的な業務効率化を実現するためには、各部門の作業手順や承認フローを詳細に分析し、無駄な工程の排除や自動化の可能性を検討する必要があります。
また、社内のパワーバランスに忖度してしまい、厳しい指摘がしづらいという問題もあります。相手が元上司だったり、社内の有力者だったりする場合に起こりがちですが、これでは客観的な監査は実現できません。
効率化の提案においては、単に作業時間の短縮を図るだけでなく、品質向上や顧客満足度の改善も同時に実現できる改善策を模索します。経営層を動かす報告として、データや事例を用いてインパクトのある改善提案を行うことが重要です。
経営目標達成への支援
内部監査は経営戦略の実行状況を客観的に評価し、目標達成に向けた軌道修正を支援します。しかし、監査業務の成果が社内で正当に評価されにくいという課題があり、「やって当たり前」と思われがちで、担当者のモチベーションが上がりにくい状況があります。
経営目標の達成支援では、単に結果を評価するだけでなく、目標設定の妥当性や実行プロセスの有効性も検証します。これにより、より現実的で達成可能な目標設定と、効果的な実行計画の策定を促進します。
また、他社の事例を知る機会がなく、監査手法が自己流になっているという問題もあります。守秘義務があるため情報共有が難しく、客観的な視点が不足する傾向があります。この課題を解決するためには、外部の専門家の知見を活用したり、業界のベストプラクティスを積極的に取り入れたりすることが重要です。
内部監査が必要な企業
内部監査の実施は、企業規模や事業特性によって法的要件が異なります。法的に義務付けられている企業と任意で実施する企業に分けて、その要件と判断基準を整理します。
法的に内部監査が求められる企業
会社法および金融商品取引法により、以下の企業には内部統制の整備が義務付けられており、実質的に内部監査の実施が必要となります。
大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)は、会社法第348条により内部統制システムの整備が義務付けられています。これには、取締役の職務執行の監督や使用人の職務執行の監視が含まれ、内部監査機能の確立が求められます。
取締役会設置会社は、会社法第327条第2項により原則として監査役の設置義務があります。監査役は取締役の職務執行を監査する役割を担い、この機能を効果的に果たすために内部監査部門との連携が不可欠です。
上場企業および上場準備企業は、金融商品取引法第24条の4の4により、内部統制報告書の提出が義務付けられています。内部統制報告書の作成には、内部監査による統制の有効性評価が必要であり、実質的に内部監査の実施が求められます。
| 企業分類 | 法的根拠 | 内部監査の位置づけ | 求められるレベル |
|---|---|---|---|
| 大会社 | 会社法第348条 | 内部統制システムの一環として必要 | 経営監視能力 |
| 取締役会設置会社 | 会社法第362条4項第6号 | 監査役監査の実効性確保のため必要 | 専門的能力・正当な注意 |
| 上場企業・IPO準備企業 | 金融商品取引法第24条の4の4 | 内部統制報告書作成のため必要 | 助言・提言能力 |
内部監査を任意で実施する企業
法的要件に該当しない中小企業でも、事業の成長や組織の複雑化に伴い、内部監査を導入するケースが増加しています。任意実施の判断基準として、以下の要因が考えられます。
組織規模の拡大により、経営者による直接的な管理が困難になった企業では、内部監査を通じた統制機能の強化が有効です。従業員数が50名を超えると、部門間の連携や情報共有に課題が生じやすくなり、内部監査による組織横断的なチェック機能の必要性が高まります。
事業の多角化や地理的分散が進んだ企業では、各事業部門や拠点の業務状況を本社が把握することが困難になります。内部監査により統一的な基準での評価を行うことで、グループ全体のガバナンス強化を実現できます。
社会的信用の向上を目指す企業では、内部監査の実施により透明性の高い経営体制をアピールできます。特に、取引先や金融機関からの信頼獲得、優秀な人材の採用などにおいて、内部監査体制の存在は重要な要素となります。
内部監査の種類と対象範囲
内部監査は対象領域や目的に応じて複数の種類に分類され、それぞれが企業の異なる側面を評価します。主要な監査種類とその特徴について詳しく解説します。
会計監査
会計監査は財務会計処理の適正性を確認する監査です。貸借対照表や損益計算書などの財務諸表に記載された内容の正確性を検証し、会計基準への準拠状況を評価します。
主要なチェック項目には、売掛金の実在性、買掛金の網羅性、現金の実査、固定資産の計上・除却処理の適正性確認、経営者の見積の妥当性などがあります。特に重要なのは、会計処理の根拠となる証憑書類の存在と内容の妥当性です。
会計監査では、経理担当者の専門知識レベルや内部統制の運用状況も評価対象となります。適切な職務分離が行われているか、承認プロセスが機能しているか、システムのアクセス権限が適切に設定されているかなど、会計不正を防止する仕組みの有効性を総合的に判断します。
システム監査
システム監査は情報システムの信頼性、安全性、効率性を評価する監査です。近年のデジタル化の進展により、システム監査の重要性は急速に高まっています。
主要な評価項目には、情報セキュリティ体制、個人情報保護対策、システムの可用性・継続性、外部委託業者の管理体制などがあります。特に生成AIやサイバーセキュリティなど、新たなリスクに対応することが重要です。
システム監査では、IT統制の有効性評価も重要な要素です。システムの変更管理、アクセス権限管理、データバックアップ・復旧手順などの統制活動が適切に設計・運用されているかを確認し、システム障害やデータ漏洩のリスクを最小化する体制の構築を支援します。
業務監査
業務監査は会計以外の業務活動全般を対象とし、業務プロセスの適法性・効率性・有効性を評価します。組織体制、業務フロー、規程・規則の整備状況、記録・資料の管理状況などが主要な確認項目です。
「固有リスク」の重要性
重要なのは、自社のビジネスモデルに特有の「固有リスク」に焦点を当てた監査を行うことです。 例えば、多数のフリーランスを活用して事業を行っている会社では、フリーランスとの契約形態や情報管理のあり方が事業の根幹を揺るがしかねない重要リスクとなります。
しかし、多くの企業では被監査部門の業務理解が浅く、踏み込んだ指摘ができないという課題があります。特に専門知識が求められる部署(情報システム部や経理部など)の監査が表面的なものになりがちです。
一般的な監査の雛形にはない項目かもしれませんが、このような固有リスクを重点的に監査しなければ、真の自浄作用が働いているとは言えません。「他社がやっているから」という理由だけでなく、「自社にとってこのリスクは重要だから監査項目に加える」といった、メリハリのある計画を立てることが重要です。
内部監査の実施手順
効果的な内部監査を実現するためには、体系的で計画的なアプローチが不可欠です。監査の各段階における重要なポイントと実践的な手法について解説します。
監査計画の立案
監査計画は内部監査の成功を左右する最も重要な要素です。監査の成否は「計画段階」で決まると言っても過言ではありません。リスク評価やチェックリストの作り込みが、監査の質を大きく左右します。
年間監査計画では、企業の事業戦略やリスク評価に基づいて監査対象を選定し、適切な監査頻度とタイミングを設定します。毎年見直しを行い、現状に即したものに更新することが重要です。
全体を網羅的にチェックするのではなく、リスクの大きさに応じて重点的に内部監査を行う「リスクアプローチ」の採用により、限られた監査リソースを最も重要な領域に集中できます。過去の監査結果、内部統制の評価、経営環境の変化などを総合的に分析し、監査優先度を決定することが重要です。
個別の監査計画では、監査目的・範囲・手法・担当者・スケジュールを明確に定義します。監査の客観性を確保するため、監査人は監査対象部門から独立した立場の者を選任し、必要に応じて外部専門家の活用も検討します。
予備調査の実施
予備調査は本監査の効率性と有効性を高めるための重要なプロセスです。監査対象部門の基本情報、業務フロー、関連規程、過去の監査結果などを事前に収集・分析します。
被監査部門との事前コミュニケーションも予備調査の重要な要素です。監査の目的や範囲を説明し、必要な資料の準備を依頼することで、本監査をスムーズに進行できます。ただし、不正調査が目的の場合は、証拠隠滅を防ぐため事前通知を行わないケースもあります。
予備調査の結果に基づいて監査プログラムを詳細化し、具体的な監査手続きやサンプリング方法を確定します。この段階で監査の焦点を絞り込むことで、本監査における時間とコストの効率化を実現できます。
本監査の実行
本監査では、予備調査で策定した監査プログラムに基づいて実地調査を実施します。書類確認、システム操作確認、現物実査、質問・ヒアリングなど、多様な監査手法を適切に組み合わせることが重要です。
監査の実施においては、監査証拠の十分性と適切性を常に意識する必要があります。発見事項については、その事実関係を正確に把握し、関連する内部統制の不備や業務プロセスの問題点を特定します。
被監査部門との建設的なコミュニケーションも本監査の重要な要素です。監査は単なる「あら探し」ではなく、組織の改善を目的とした活動であることを明確にし、被監査部門の協力を得ながら監査を進めます。
報告と改善フォロー
監査結果の報告は、発見事項の重要性と改善の緊急度に応じて適切な形式で行います。軽微な事項については口頭報告で済ませ、重要な事項については書面による正式な報告書を作成します。
経営層を動かす報告を意識することが重要です。監査は指摘をして終わりではありません。経営層に問題の重要性を理解してもらい、全社的な改善活動に繋げてこそ意味があります。データや事例を用いて、インパクトのある報告を心がけましょう。
フォローアップ監査により改善状況を継続的に確認し、改善が不十分な場合は追加の対応策を検討します。改善が進まない根本的な原因を分析し、組織的な問題がある場合は経営陣への報告・提言を行います。
内部監査を成功させるポイント
実効性の高い内部監査を実現するためには、単に手順を踏むだけでなく、戦略的なアプローチと継続的な改善が必要です。特に形骸化を防ぎ、真に企業の成長に貢献する「攻めの内部監査」を実現するためのポイントを解説します。
IPO準備期における段階別アプローチ
IPO準備企業における内部監査は、上場までの限られた時間の中で最大の効果を得るため、段階的なアプローチが重要です。
立ち上げ期(N-2期):「ないない尽くし」の現実的な乗り越え方
IPO準備を始めたばかりの上場の2期前(N-2期)は、事業の成長にリソースを集中させたい時期です。内部監査に専任の担当者を置くのは難しく、多くは管理部門の担当者が兼務で手探りで進めているのが実情です。
この「人も時間も知見もない」状況を乗り切る鍵は2つあります。
鍵①:アウトソーシングの賢い活用
知識も経験もない中でゼロから体制を構築するのは非常に困難です。専門知識を持つ外部のコンサルティング会社などをアウトソーシング先として活用することが有効です。
ただし、絶対に避けなければならないのが「丸投げ」です。アウトソーサーに丸投げになってしまうと、会社側で何をやっているか全くわからなくなり、対外的に説明ができなくなってしまいます。
重要なのは「頭脳の部分は自社で握る」という意識です。計画の策定や監査結果の評価といった根幹部分には主体的に関与し、「なぜこの監査を行うのか」を自分の言葉で説明できる状態を保つ必要があります。
鍵②:まずは「1周回す」ことを目指す
立ち上げ期は、完璧を目指す必要はありません。どの会社でも共通して求められる基本的な項目(稟議規程の遵守、労務管理の適切性など)について、とにかく1周やり切ってみることが重要です。
実際にやってみると、「そもそも規程が周知されていない」「サンプルデータすら集まらない」といった想定外の課題が次々と見つかります。N-2期は、こうした組織の課題を洗い出し、改善のサイクルを回し始めるための助走期間と捉えることが大切です。
本格運用期(N-1期):「チェックリストを埋めるだけ」からの脱却
内部監査の運用が本格化するN-1期になると、多くの企業が「網羅的に、漏れなくやらなければ」という意識に囚われ、チェックリストを埋めることが目的になってしまいがちです。
しかし、審査を突破するためには、一歩進んだ「リスクアプローチ」の視点が不可欠です。
「内製化」と「アウトソーシング」の最適な選択
形骸化した内部監査から脱却するためには、自社に最適な実施体制を選択することが重要です。以下の3つの選択肢それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に応じた最適解を見つけましょう。
| 実施体制 | 概要 | メリット | デメリット | 適用場面 |
|---|---|---|---|---|
| 内製化 | 自社の社員のみで内部監査の全てを行う | ・自社業務への理解が深い ・コストを抑えられる |
・監査経験や専門知識が不足しがち ・社内の人間関係で指摘しづらい場合がある |
十分な人材と経験がある場合 |
| コソーシング (一部外注) |
計画策定や一部の専門分野など、業務の一部を外部に委託する | ・自社の強みと外部の専門性を両立できる ・必要な部分だけサポートを受けられる |
・委託先との連携や管理が必要になる | 専門知識に不安があるが基本体制はある場合 複数拠点の監査を実施するために大きなリソースが必要な場合 |
| フルアウトソーシング (すべて外注) |
計画から報告まで、内部監査業務の全てを外部に委託する | ・専門家による質の高い監査が実現できる ・客観的な視点で忖度ない指摘が可能 ・他社事例を参考にできる |
・コストがかかる ・初期段階で業務理解のための時間が必要 |
抜本的な体制刷新が必要な場合 |
「理想は内製化」としつつも、「チェックリストの形骸化などの懸念がある場合は、アウトソーシングの活用も有効な選択肢」です。
例えば、リソースは足りていても専門知識に不安がある場合は「計画フェーズだけ」をコソーシングしたり、一度業務全体を刷新したい場合は「期間限定で」フルアウトソーシングを活用し、最適なやり方を学んでから内製化に戻すといった柔軟な活用法も考えられます。
形骸化を防ぐ3つの重要ポイント
実効性のある内部監査を実現するための3つの重要ポイントは以下の通りです。
- 監査の成否は「計画段階」で決まる リスク評価やチェックリストの作り込みが、監査の質を大きく左右します。毎年見直しを行い、現状に即したものに更新しましょう。過去のチェックリストを毎年使い回すのではなく、環境変化や新たなリスクを反映した動的な計画立案が重要です。
- 「外部の視点」を積極的に取り入れる 社内のメンバーだけでは、どうしても視野が狭くなりがちです。他部署とのローテーションや、必要に応じて外部専門家の知見を活用することで、新たな気づきが生まれます。社内のパワーバランスに忖度せず、客観的な監査を実現するためにも外部の視点は重要です。
- 「経営層を動かす報告」を意識する 監査は、指摘をして終わりではありません。経営層に問題の重要性を理解してもらい、全社的な改善活動に繋げてこそ意味があります。データや事例を用いて、インパクトのある報告を心がけることで、監査業務の成果が社内で正当に評価されるようになります。
まとめ
内部監査は企業の持続的成長と価値創造を支える重要な経営機能です。単なる「チェック作業」ではなく、企業の自浄作用を強化し、経営目標の達成に直接貢献する戦略的なツールとして位置づけることが重要です。
現代の内部監査に求められる変化:
- 責任範囲の拡大:デュアルレポーティングによる監視機能の強化
- スキルの高度化:助言・提言能力を含む専門的能力の必要性
- 新たなリスクへの対応:生成AIやサイバーセキュリティなど環境変化への適応
形骸化を防ぐための重要な視点:
- 過去のチェックリストの使い回しからの脱却
- 自社固有のリスクに焦点を当てたリスクアプローチの実践
- 社内のパワーバランスに忖度しない客観的な監査の実現
- 経営層を動かす効果的な報告の実施
実施体制の最適化:
- 内製化、コソーシング、フルアウトソーシングの特徴を理解した選択
- 「頭脳の部分は自社で握る」原則の維持
- 外部の専門性と客観性の効果的な活用
この記事を読んでくださったあなたは、ぜひ自社の内部監査のチェックリストを改めて見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。そして、もし行き詰まりを感じたら、外部の専門家の意見を聞いてみるのも一つの有効な手段です。
まずは貴社の事業における最も大きなリスクは何か、そして現在の内部監査計画がそのリスクにしっかりと対応できているかを、ぜひチームで議論してみてください。自社の言葉でリスクを語り、それに対応する仕組みを構築することが、真に実効性のある内部監査の実現と企業価値向上への確かな一歩となるはずです。